ニュースでは戦争についての報道が毎日なされている。
見るたびに心が痛むが、歴史を振り返れば戦争により技術が向上し、私たちが日々当たり前に思っているモノとして形を変えていることを知っているだろうか?
食卓では毎日といっていいほどお世話になっているサランラップもそのひとつ。
今回は戦争により発達した日用品や医療技術をご紹介します。
戦争により発明された日用品
1、サランラップ
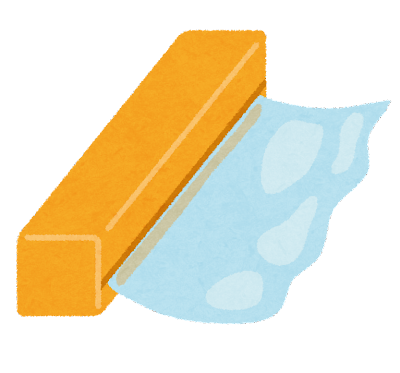
食卓では、毎日使う人も多いサランラップ。
無くてはならない存在ですよね。
しかし、もともとは食品用ではなく、戦場でつかう「銃弾」を湿気から守るために開発されました。
2、インスタントコーヒー

世界で最初のインスタントコーヒーは1771年に英国で発明され、
その後、南北戦争の時に兵士に配られました。
戦争が終わってからも、インスタントコーヒーは母国に持って帰り、一般家庭に消費されるようになりました。
3、缶詰・レトルト食品

今から約200年前、金属缶やガラスの瓶の中に食物を入れて密封し、加熱殺菌する保存方法をフランス品が発明しました。
その後、その技術は進化しながら1821年にアメリカに渡り、缶詰の製造が本格化。
1861年の南北戦争で軍事用の食糧として急激に需要が高まり、その後一般家庭へと届くようになりました。
4、正露丸

家庭の常備薬として有名な「正露丸」。こちらは日露戦争がきっかけになっています。
5、腕時計
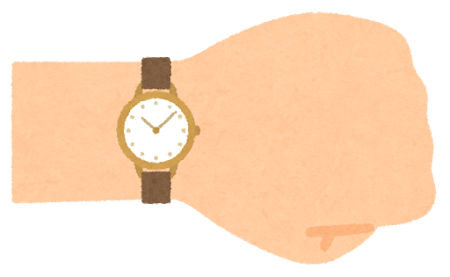
1700年代は懐中時計が使われていました。
その後19世紀になり、通信技術が発達します。戦争も時間に合わせて命令が下るようになり、懐中時計をポケットから取り出し、確認するのが不便だったことで腕に巻き付けたことが始まりです。
今の生活に欠かせない日用品のほとんどが戦争から生まれました。
ここだけフォーカスしたら、戦争も悪い事ばかりではないのかもしれませんね。
では、次は医療についてお話します。
戦争により進化した医療
1、遠隔手術ロボット

台湾戦争をきっかけに、遠隔地でも外科的手術が行えるように、アメリカを中心として開発されました。
2、義肢

義肢の発達は戦争と密接な関係にあり、負傷した兵士が戦いに戻るためや、その後の生活に戻るために社会的な機能をもたせるために進化しました。
義手の起源は紀元前からあり、そこから18世紀までは「鉄製」でした。
19世紀に入り指が開くバネ付きになり、現代では筋肉の反応を読み取り、動くようにまで進化しています。
3,エピテーゼ
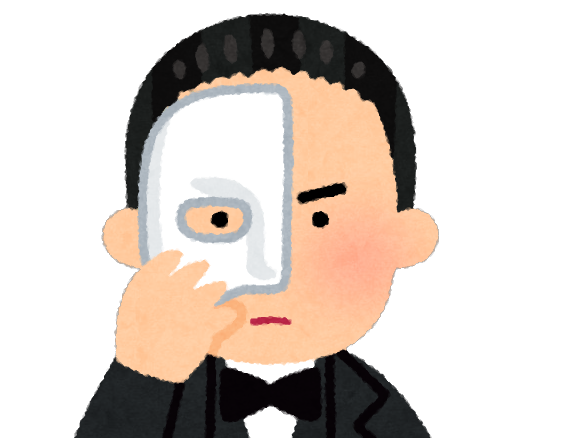
エピテーゼとは失った身体の一部を審美的な回復をさせるためのリアルな人工ボディです。
第一次世界大戦では火炎放射器で顔を焼かれた帰還兵が何万人もいました。
顔を失くした兵士たちの社会復帰のために、リアルな仮面をつくり精神的に支えたのが始まりと言われています。
現代では顔だけでなく、指先やガンによる審美回復としての役目を果たしています。
まとめ
戦争により発達した日用品や医療技術をご紹介しました。
皮肉なことに、歴史を振り返れば戦争により技術が向上してきました。
その技術は、現代では役目が変わり、私たちが日々当たり前に思っているモノとして形を変えてきました。
現代でも戦争が始まってしまったわけですが、無駄な争いが一日でも早く終わることを願います。
おまけ
日本は終戦から77年が経ちました。
当時を語る人がほとんどいらっしゃらなくなってきましたが、彼らのおかげで今を不自由なく生きられているのです。
今回のおまけは「エピテーゼ」についてです。
エピテーゼは米国などではポピュラーなサービスです。
それは戦争があるから。
本題にも明記しましたが、エピテーゼは戦争により顔を失くした兵士が社会復帰するために発展した技術です。
日本ではまだまだ知られておらず、また製作できる人も一握りです。
顔のパーツからカタチを変え、日本では指先を切断されてしまった方や、乳がんでお胸をなくされてしまった方、生まれつき耳が小さい小耳症の方、指が短い短指症の方といったひとたちにエピテーゼは作られています。
興味深いな。製作に興味をもったと思われたら、エピテスクールがオススメです。

